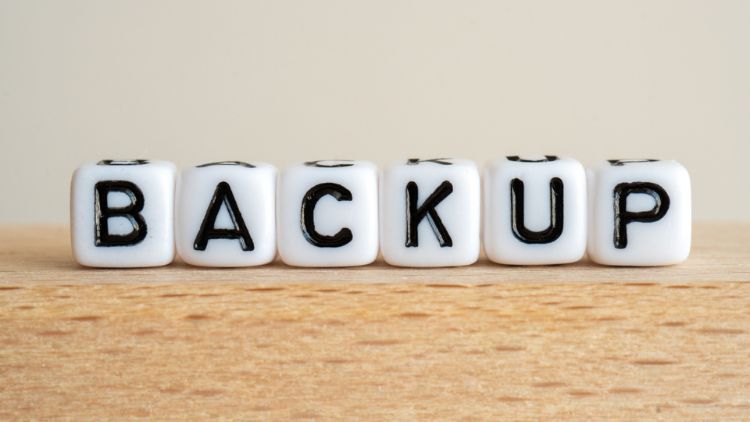
2025.09.12
- コラム
アルコール点呼の記録、何年保存?保存期間・方法・違反リスクまで完全解説
アルコールチェックや点呼記録の管理は、安全運転管理者にとって避けては通れない業務のひとつです。特に、保存期間や記録方法については「なんとなく1年くらい保管している」という曖昧な運用が多く見受けられます。
しかし、2022年(令和4年)の法改正以降、点呼やアルコールチェックの記録保存は義務となり、保存期間や方法にも明確なルールが設けられました。にもかかわらず、「紙で残せばいいのか」「データ保存でも大丈夫か」など、正しい運用に不安を感じている担当者も少なくありません。
この記事では、点呼記録の保存に関する法律上の根拠・保存形式の選び方・記録内容のポイント・業種ごとの違いなどを、実務に即してわかりやすく解説します。法令順守をベースにしつつ、日々の業務負担を軽減しながら管理体制を整えたい方に役立つ内容です。
点呼記録の保存期間は法律で「1年間」と明記されている
アルコールチェックや点呼の記録は、法令上「1年間」保存することが義務付けられています。これは努力義務ではなく、明確な保存義務です。実施した記録を1年未満で破棄してしまうと、保存義務違反と見なされるおそれがあります。
多くの企業で「なんとなく1年間」という感覚で運用されていますが、実際には道路交通法施行規則の中に根拠が示されています。まずはこの保存期間の法的な裏付けと、実務で起こりがちな誤解を整理しましょう。
「保存期間1年」の根拠はどこにあるのか?
アルコールチェックに関する保存期間は、令和4年4月に改正された「道路交通法施行規則」および「警察庁通達」により定められています。これにより、安全運転管理者が行う点呼・アルコールチェックの記録は、最低でも1年間保管することが法律で義務付けられました。
保存対象となるのは、以下のような記録です。
●アルコール検知の実施日時
●確認者と被確認者(運転者)の氏名
●使用車両の情報
●検知方法と結果
●指示事項 など
このような情報を適切に記録し、1年間保存しておくことが求められます。期限を過ぎた記録は破棄しても問題ありませんが、保存期間内に紛失・未記録となると、監査時に不備と見なされる可能性があります。
保存期間の起算日は「作成日」が実務上の標準
法律上では「保存期間の起算日は〇〇日から」といった具体的な定義は示されていません。ただし、多くの専門機関や企業運用のガイドでは、記録を作成した日(アルコールチェックを行った当日)から1年間とする運用が標準となっています。
例えば、2025年9月1日に実施・記録したアルコール点呼は、2026年8月31日まで保存する必要があるという扱いです。
この「作成日起算」が一般的である理由は、点呼やアルコールチェックが日々の運行業務と密接に結びついており、実施当日=記録作成日であることが明確だからです。起算日があいまいになると保存管理が煩雑になるため、実務上は「実施日=起算日」で管理するのが最もシンプルで確実です。
紙でもデジタルでもOK?保存方法は指定されていない
点呼記録の保存期間が法律で「1年間」と定められている一方で、その保存方法については、法令上の明確な指定はありません。紙の書類として保存しても、パソコンやクラウドなどのデジタル形式で保存しても問題ないとされています。
この柔軟性は、中小企業を含めた多様な業種・体制の事業者が、それぞれに合った方法で法令対応できるようにするための配慮です。ただし、形式が自由だからといって、どんな保存方法でも良いというわけではありません。
特にデジタル保存を行う場合には、改ざん防止や保存性の確保など、実務上の注意点があります。
デジタル保存にする際の実務上の注意点
電子的に保存する場合、次のようなリスクを防ぐ措置を講じることが求められます。
●改ざんされない状態で記録すること
保存後に記録内容を書き換えられないようにする必要があります。たとえば、Excelファイルで記録した後にPDF形式で保存する、専用の記録ソフトを使うといった対応が現実的です。
●バックアップを確保すること
データの消失や破損に備えて、外部メディアやクラウドに二重保存する運用が推奨されます。
●閲覧・検索できる状態で保存すること
監査や確認時にすぐに提示できるよう、ファイル名やフォルダ構成も整理しておく必要があります。
これらはすべて「義務」ではなく「望ましい対応」ですが、実際にトラブルが起きたときの対応力を左右する重要なポイントです。
保存形式ごとのメリット・デメリット比較
保存形式は自由ですが、それぞれに特徴と注意点があります。導入時には、以下のような観点で比較しておくと、自社に合った保存方法を選びやすくなります。
紙保存の管理コストと保存スペースの課題
●低コストで導入可能
特別な機器やソフトが不要なため、小規模な事業者でもすぐに始められます。
●記録の改ざんがしにくい
一度記入した用紙は物理的に残るため、不正防止につながります。
●保存スペースと管理負担が大きい
1日1回×複数名の点呼記録を1年間保管すると、ファイルや棚のスペースを圧迫します。過去記録を探す手間も無視できません。
電子保存の利点と導入時の注意点
●検索・共有が容易
ファイル管理やクラウドを使えば、必要な記録をすぐに探し出せます。複数拠点での情報共有もスムーズです。
●省スペース・業務効率化に直結
紙保管が不要になり、事務所スペースを有効活用できます。定型業務の自動化も可能です。
●システム選定と初期設定が重要
保存ルールが社内で曖昧だと、抜け漏れや不整合の原因になります。ツール導入時は運用マニュアルの整備も欠かせません。
紙とデジタル、どちらが「正解」というわけではなく、事業規模・業種・拠点数・人員体制などに応じて最適な方法を選ぶことが重要です。
記録内容に不備があると保存の意味がない
点呼記録は「保存すること」自体が目的ではありません。法律で求められているのは、必要な情報を正確に記録し、適切に管理することです。形式だけ整えていても、記録内容に不備があれば、保存義務を果たしているとは言えません。
たとえば、「運転者の名前が記載されていない」「アルコール検知の結果が空欄」などの不完全な記録では、監査時に不備として指摘されるリスクがあります。記録ミスや記載漏れを防ぐためには、何を記載すべきかを正しく理解しておく必要があります。
保存すべき必須項目は「9つ」
国土交通省や各地の運輸支局が提供するモデル様式に基づき、点呼・アルコールチェックの記録に含めるべき項目は以下の9つが基本です。2023年12月以降、「アルコール検知器の使用有無」も法令上の必須項目として追加されました。
●運転者の氏名
運転業務に就く対象者を特定できるよう、フルネームで記載します。
●確認者(安全運転管理者)の氏名
誰が点呼・チェックを行ったかが明確になるよう記録します。
●確認日時
点呼やアルコール検知の実施日時を正確に記載します。
●使用車両の情報
車両番号や管理番号など、使用する車両を特定できる情報を記載します。
●アルコール検知の方法
検知器の使用、顔色や動作の確認などの手法を明示します。
●検知結果(酒気帯びの有無)
「酒気なし」または「酒気帯びの疑いあり」など、明確に記載します。
●アルコール検知器の使用有無
検知を行う際に、アルコール検知器を使用したかどうかを明示します。
●管理者による指示内容
必要に応じて、運転中止や代替手配などの指示内容を記録します。
●その他特記事項
体調不良・遅刻・点検漏れなど、記録に残すべき事項があれば記載します。
これら9項目を網羅して初めて、法令に適合した記録として認められます。記載漏れがあると、監査時に不備と見なされるリスクが高まります。
写真・動画記録は保存対象に含めるべきか?
法律上、アルコールチェックの写真や動画の保存が必須とされているのは一部の業種(例:貸切バス)に限られます。通常の事業者においては、写真・動画の保存までは義務ではありません。
ただし、直行直帰や遠隔地勤務が多い場合、写真や動画による確認が「記録の補完資料」として有効です。たとえば、以下のようなケースで活用されています。
●モバイル端末で撮影した検知器の表示画面と本人の顔写真をセットで保存
●オンライン点呼時に録画を残しておく
●通信アプリでリアルタイム映像を確認し、録画を自動保存する
これにより、「本当にチェックしたのか?」「誰がやったのか?」という疑念を払拭できると同時に、社内監査や労務トラブル対策にも役立ちます。
ただし、動画・写真の保存期間や形式に関するルールは事業形態によって異なるため、自社の業種と対応義務の有無を事前に確認することが重要です。
業種によって保存ルールが変わる場合がある
アルコール点呼記録の保存期間や方法は、基本的にはすべての事業者に対して同じ「1年間・保存形式自由」の原則が適用されます。しかし一部の業種、特に運輸・旅客輸送に関連する分野では、より厳しい保存要件が課されているケースがあります。
たとえば、貸切バスや観光バスなどを運行する事業者は、通常の企業よりも高い安全性が求められるため、記録内容や保存期間が強化されています。業種による違いを知らずに一般ルールだけを適用していると、重大な法令違反に繋がるおそれもあります。
貸切バス業界は90日+3年保存が義務化
2024年4月以降、国土交通省の通達により、貸切バス事業者にはアルコールチェックに関する映像・音声記録の保存義務が新たに追加されました。具体的には、以下のような対応が求められています。
●アルコールチェック時の映像・写真を記録
対面での確認が難しい場合には、本人の顔・検知器の数値が確認できる写真や動画を撮影します。
●記録は最低90日間保存
映像や写真データは、実施日から90日間以上保存する必要があります。
●点呼記録全体は3年間の電子保存が原則
運行管理に関するデータは、電子ファイルで3年間保存し、提出を求められた際にすぐ提示できる状態にしておく必要があります。
このように、貸切バス事業では「映像記録の義務化+長期保存」が明文化された業界ルールとなっており、一般企業とは対応が異なります。
業種をまたぐ場合は最も厳しい基準に合わせるのが安全
複数の業種・事業形態をまたいでいる企業では、すべての事業に共通する最低限の基準を設けるだけでは不十分です。
たとえば、社内に貸切バス部門と一般配送部門が併存しているような企業の場合、それぞれの業種ごとに保存義務の内容が異なるため、対応ルールがバラバラになる可能性があります。
そのような場合は、社内全体で最も厳しい保存基準に合わせて統一的に管理することが、実務上のミスを防ぐうえで有効です。
●一部の部門だけが写真保存していると、記録にばらつきが出る
●保存期間が部署ごとに異なると、誤廃棄や対応漏れのリスクが高まる
●システムやフォーマットが統一されていないと監査対応に時間がかかる
こうした事態を避けるためにも、「最も厳しい基準を標準化する」という運用ルールが、実務上もっとも安全で効率的です。
保存義務違反は重大なリスクに直結する
点呼記録の保存は、単なる事務処理ではなく、法令順守と企業の安全管理体制を証明する重要な業務です。記録の未保存や内容の不備、保存期間の超過は、安全運転管理者制度に基づく義務違反と見なされる可能性があります。
特に事故や違反が発生した際には、過去の記録が監査や調査の対象となり、企業としての信頼性を大きく損なうリスクがあります。日頃から適切に記録・保存を行っていなければ、罰則や行政指導の対象になることもあり得ます。
安全運転管理者の解任や罰金の可能性
アルコールチェックや点呼記録の保存義務に違反した場合、安全運転管理者本人や所属企業には次のようなリスクが発生します。
●安全運転管理者としての適格性を問われる
記録保存義務を果たしていないことが明らかになると、監督官庁から解任命令が出される場合があります。
●企業に対して罰則が科される
点呼記録の保存義務違反は、道路交通法に基づき最大50万円以下の罰金対象となる可能性があります。
●指導や改善命令の対象となる
悪質または繰り返し違反がある場合には、事業改善命令や業務停止処分など、より重い行政処分を受けることもあります。
これらのリスクは、法的な処分にとどまらず、取引先・顧客・従業員からの信頼を失う要因にもつながります。記録の保存という基本を怠ることで、大きな損失を被ることになりかねません。
チェックが入るタイミングと監査の実態
「記録の保存がきちんと行われているか」は、企業が安全運転管理者を設置している以上、いつでも確認される可能性がある事項です。次のような場面で、保存状態がチェックされます。
●定期的な行政監査・巡回指導
運輸支局や警察の指導員が、定期的に企業の管理体制を確認することがあります。
●交通事故や飲酒運転の発生時
自社または委託先で事故が起きた場合、過去の記録を調査されることがあり、その際に記録不備が重大な問題として扱われる可能性があります。
●他社の違反事例からの波及調査
類似業種で保存違反が多発している場合、業界全体に対する調査・監査が強化されることがあります。
これらに備えるためには、記録を保存するだけでなく、「いつでも提示できる状態に整えておく」ことが求められます。日常的な記録管理の質が、そのまま企業のコンプライアンス評価に直結します。
実務に役立つテンプレートと保存管理のコツ
点呼記録の保存は、法律に従って正しく行うだけでなく、日々の業務の中で無理なく・確実に続けられる仕組みにすることが重要です。そのためには、あらかじめ整ったフォーマットを使い、記録の抜け漏れを防ぎ、運用を「習慣化」する工夫が欠かせません。
国や自治体、業界団体が提供するテンプレートを活用すれば、法律に沿った内容を確実に記録できるうえ、自社の運用にも柔軟に対応できます。
テンプレートを使えば記録の抜け漏れを防げる
国土交通省や都道府県の運輸局では、安全運転管理者用の点呼記録テンプレートを公開しています。これらは、法律に基づいて作成されているため、記載すべき項目がすべて網羅されています。
テンプレート活用のメリットは以下の通りです。
●必要な項目が一目で分かる
記入欄が定型化されており、チェック漏れや記録忘れを防げます。
●記録の質が均一になる
誰が担当しても一定の基準で記録され、引き継ぎや監査にも強くなります。
●電子化やクラウド化にも対応しやすい
Excel形式やPDFなどで配布されているため、デジタル記録への転用も容易です。
また、地域ごとに若干の違いがある場合もあるため、自社が所属する地域の運輸局サイトや業界団体から最新の様式を確認することが重要です。
保存管理のチェックリストを作って習慣化する
テンプレートを活用しても、「記入し忘れ」「保存し忘れ」が発生する可能性はゼロではありません。そのため、記録から保存までの一連の流れをチェックリスト化し、日常業務に組み込むことで、ミスや漏れを防ぎやすくなります。
チェックリストの一例:
●記録対象の全員が点呼済みか確認
●9項目すべてが記載されているか確認
●紙・電子どちらで保存するか確認
●保存場所(ファイル名・保管棚)を統一
●保存期間満了分の記録は適切に破棄・アーカイブ
このようなチェックポイントを運用マニュアルや朝礼資料に組み込み、現場のスタッフが自然に確認できる仕組みを作ることが、記録管理の質を長期的に維持するコツです。
まとめ

アルコール点呼や安全運転管理の記録は、ただ残せばよいというものではありません。記録すべき内容を正しく把握し、法律で定められた1年間の保存を確実に実行することが、企業の信頼と安全を守る土台になります。
保存形式は紙でも電子でも自由ですが、業種によっては動画や写真の保存義務が加わるなど、対応の厳しさは異なります。特に、複数の業種にまたがる企業では、もっとも厳しい基準に合わせた一元管理がリスク回避につながります。
記録の抜けや誤りを防ぐには、テンプレートやチェックリストの活用が効果的です。これらを運用に組み込み、無理なく継続できる体制を整えることが、コンプライアンス対応の第一歩です。
点呼記録の保存は、「やらなければいけない業務」ではなく、「安全と信頼を守る企業の証明」です。今一度、自社の保存体制を見直し、法令と実務の両面から、安心できる運用を整えていきましょう。
